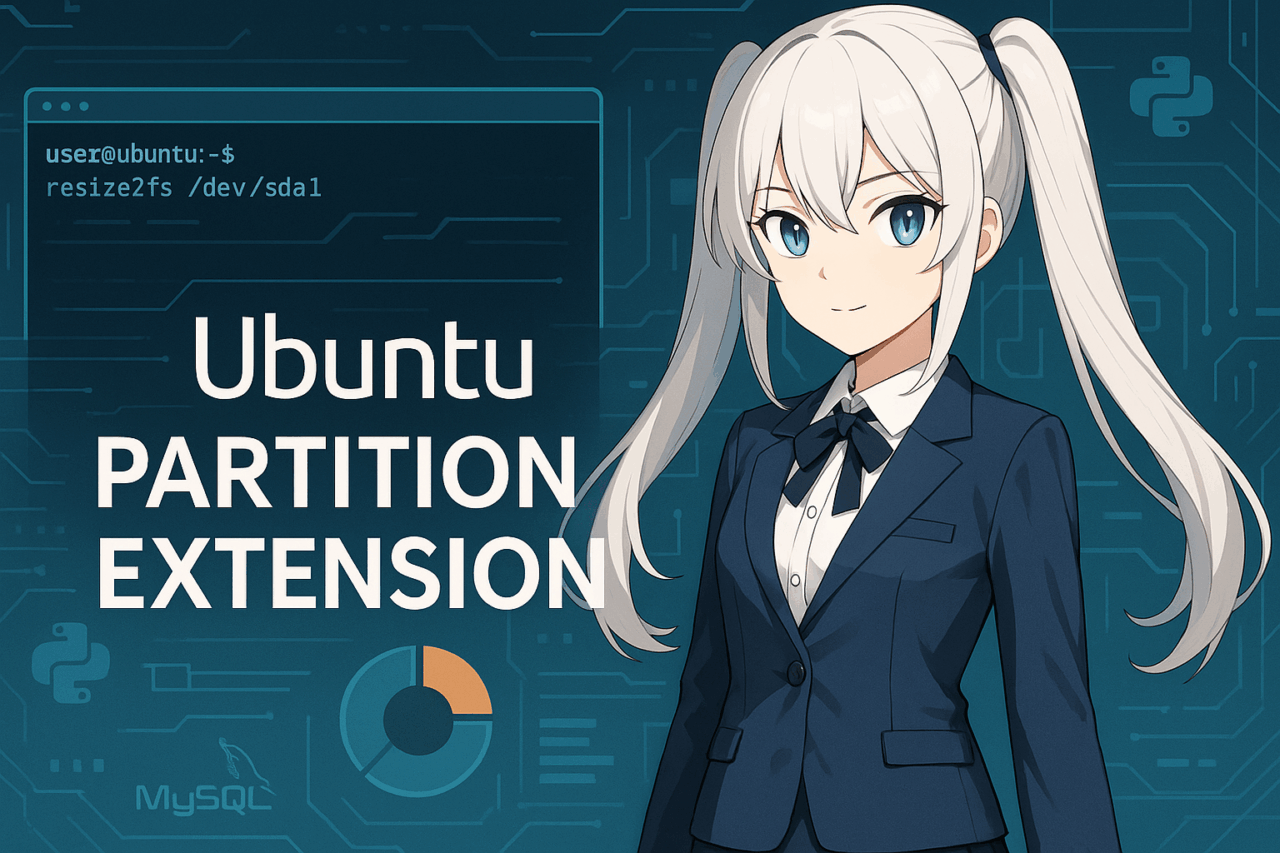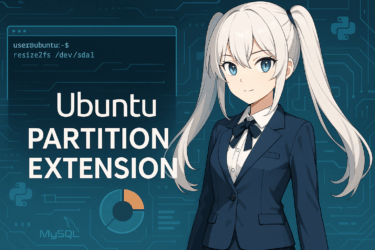1. はじめに
Ubuntuを利用していると、「ディスク容量が足りなくなった」「新しいアプリをインストールしたいのに空き領域がない」といった場面に直面することがあります。こうした場合に役立つのが「パーティション拡張」という操作です。パーティション拡張とは、既存のディスク領域(パーティション)をより大きくし、ストレージ容量を効率よく使うための方法です。
特に、Ubuntuはサーバー用途からデスクトップ用途まで幅広く利用されており、仮想マシンやVPS(仮想専用サーバー)、デュアルブート環境など、さまざまな状況でパーティション管理が必要になることがあります。しかし「どの方法で拡張すればよいのか」「操作を間違えるとデータが消えてしまうのでは」と不安に思う方も少なくありません。
本記事では、Ubuntuでパーティションを拡張したい方に向けて、シンプルな手順から、LVM環境や仮想環境での応用例まで、できるだけ分かりやすく解説します。また、パーティション操作には注意点も多いため、事前準備や安全に作業を進めるためのポイントについても触れていきます。
「Linuxのコマンド操作は初めて」という方から、「以前、他のディストリビューションでパーティション操作をしたことがある」という中級者まで、幅広い層の方に役立つ内容を心がけました。
パーティション拡張の作業は慎重さが求められますが、正しい手順を知っておくことで大切なデータを守りつつ、ストレージ容量を有効活用できるようになります。
2. パーティション拡張の前提知識
Ubuntuでパーティションを拡張する前に、基本的な知識を身につけておくことで、作業ミスやトラブルを防ぎやすくなります。ここでは、パーティションやファイルシステムの基礎、LVMの有無、そして最近のUbuntuにおけるパーティション構成の傾向について解説します。
2.1 パーティションとは何か?
パーティションとは、物理的なハードディスクやSSDなどの記憶装置を、仮想的に複数の区画に分けて管理する仕組みです。たとえば、ひとつのディスクを「システム用」「データ用」などに分割でき、それぞれ独立した領域として扱えます。Ubuntuのシステムファイルやユーザーデータ、スワップ領域なども、パーティションごとに分かれている場合が多いです。
2.2 パーティションテーブルの種類(GPTとMBR)
ディスクのパーティション構成を記録する方式には主に「GPT(GUIDパーティションテーブル)」と「MBR(マスターブートレコード)」の2種類があります。
- MBR:古くから使われている方式で、最大2TBまでのディスク容量と、最大4つまでのプライマリパーティションが作成可能です。
- GPT:比較的新しい方式で、2TBを超える大容量ディスクや、128個以上のパーティションにも対応しています。現在のUbuntuではGPTが主流です。
ご自身の環境がどちらか分からない場合、sudo parted -l などのコマンドで確認できます。
2.3 LVM(論理ボリューム管理)の有無
Ubuntuでは、パーティションを直接拡張する場合と、LVM(Logical Volume Manager)という柔軟なボリューム管理を使う場合があります。
- LVMなし(通常のパーティション)
ext4などのファイルシステムがパーティション上にそのまま作られている一般的なケースです。 - LVMあり
物理ディスクの上に「物理ボリューム(PV)」を作り、それを束ねて「ボリュームグループ(VG)」とし、その上に「論理ボリューム(LV)」を作る仕組みです。容量の拡張や縮小が柔軟にできるため、近年のサーバー用途やクラウド環境で多く使われています。
どちらの方式を使っているかで、パーティション拡張の手順が変わります。
2.4 Ubuntuにおけるパーティション構成の傾向
Ubuntuのインストール時にLVMを利用するかどうかは選択可能ですが、近年のサーバー用途(特に20.04以降)ではLVMの利用が推奨・標準化されてきています。
一方、デスクトップ用途やデュアルブート環境では、従来どおりのシンプルなパーティション構成(ext4単体)も多いです。
2.5 パーティション拡張時の注意点
パーティション拡張を行う前に、必ず「未割り当て領域(unallocated space)」がディスク上に存在している必要があります。パーティションの隣接位置やディスク構成によっては、拡張ができない場合もあるため、まずは現状のディスク構成を lsblk や parted コマンドで確認しましょう。
また、重要なデータは事前に必ずバックアップを取ることを強くおすすめします。操作ミスやトラブルでデータが消失した場合でも、バックアップがあれば安心して作業を進めることができます。
3. 拡張方法別に整理
Ubuntuでのパーティション拡張は、利用している環境やディスクの構成によって手順が異なります。ここでは、代表的な4つのケース――非LVM環境、LVM環境、VPSやクラウドなどのオンライン環境、そしてデュアルブート環境について、それぞれわかりやすく手順を解説します。
3.1 非LVM(ext4)環境でのパーティション拡張
最も一般的なのが、LVMを使わず、ext4などのファイルシステムを直接パーティション上に作成している場合です。
- ディスクのサイズを増やす
- 仮想マシンやVPSの場合、まず管理画面でディスク容量を追加します。
- 物理PCの場合は、未割り当て領域を用意します。
- パーティションの拡張
- ターミナルで
sudo partedやsudo fdiskを利用し、対象パーティションを拡張します。 - partedの場合、次のようなコマンドを使います(例:/dev/sda1を拡張する場合)
sudo parted /dev/sda (parted) resizepart 1 <新しい終了位置(例:100%)>
- ファイルシステムの拡張
- パーティション拡張後、ファイルシステム自体も拡張する必要があります。
- ext4の場合、
resize2fsコマンドを実行します。sudo resize2fs /dev/sda1 - これで領域がファイルシステムに反映されます。
- 拡張の確認
- 拡張が完了したら、
df -hで増加したディスク容量を確認しましょう。
3.2 LVM環境でのパーティション拡張
LVM(Logical Volume Manager)を利用している場合は、より柔軟に容量の拡張が可能です。
- ディスクのサイズを増やす
- まず、物理ディスクや仮想ディスクのサイズを拡張します。
- 物理ディスクの場合は未割り当て領域を確保します。
- 物理ボリューム(PV)の拡張
- 新たに追加した領域をLVMの物理ボリュームとして認識させる必要があります。
sudo pvresize /dev/sda2 - (デバイス名は環境によって異なります)
- 論理ボリューム(LV)の拡張
- 拡張したい論理ボリュームを指定して容量を増やします。
sudo lvextend -l +100%FREE /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv -l +100%FREEで利用可能な全領域を割り当てます。
- ファイルシステムの拡張
- LVM上のパーティションにext4を使っている場合、
resize2fsで拡張します。sudo resize2fs /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv
- 確認
df -hやlsblkで、拡張された容量が反映されていることを確認しましょう。
3.3 VPSやクラウド環境でのオンライン拡張
VPSやクラウドでは、サーバーを再起動せずにパーティション拡張を行いたい場面も多いです。その際は、growpartコマンドなどを使うと便利です。
- ディスクサイズ拡張
- プロバイダの管理画面でディスク容量を追加します。
- パーティションの拡張(growpart)
- cloud-utilsパッケージが導入されている場合は、
growpartコマンドが利用可能です。sudo growpart /dev/sda 1 - これでパーティション(例:/dev/sda1)が自動的に拡張されます。
- ファイルシステムの拡張
- 続けて
resize2fsでファイルシステムも拡張します。sudo resize2fs /dev/sda1
- 確認
df -hで拡張を確認します。
3.4 デュアルブート(Windows/Ubuntu)環境での調整
WindowsとUbuntuを同じディスクにインストールしている場合、未割り当て領域がパーティションの隣にないと、拡張できないことがあります。
- 未割り当て領域の移動
- Windowsのパーティション編集ツール(MiniTool Partition Wizardなど)を使い、未割り当て領域をUbuntuパーティションの隣に移動します。
- Ubuntuからの拡張
- 上記の手順でパーティションの拡張を行います。
- データのバックアップ必須
- 特にデュアルブート環境では、トラブルが起きやすいため、作業前のバックアップは必須です。
4. トラブルシューティング・FAQ
パーティション拡張の作業中や前後には、さまざまな疑問やトラブルが発生することがあります。ここでは、よくある質問や典型的なトラブル、エラーとその対処法についてまとめます。
4.1 よくある質問(FAQ)
Q1. Free space(未割り当て領域)が見つかりません。どうすればいいですか?
A. パーティション拡張には「未割り当て領域」が必要です。lsblkやsudo parted /dev/sda print freeコマンドでディスクの状態を確認し、未割り当て領域が存在しない場合は、不要なパーティションを削除して空き領域を作るか、仮想環境であればディスク容量自体を追加してください。
Q2. LVMじゃない場合でもpvresizeやlvextendは必要ですか?
A. LVMを使っていない場合は、pvresizeやlvextendは不要です。ext4などの通常パーティションなら、「パーティション拡張→ファイルシステム拡張」の手順でOKです。どちらを使っているかは、lsblkやsudo pvsコマンドで確認できます。
Q3. パーティションの隣に未割り当て領域がありません。どうすれば拡張できますか?
A. パーティション拡張は、隣接する未割り当て領域が必要です。未割り当て領域が遠くにある場合は、Windowsの「MiniTool Partition Wizard」などでパーティションの順序や位置を調整してください。
物理マシンの場合は、データのバックアップを必ず行い、慎重に操作しましょう。
Q4. Ubuntuの稼働中にパーティション操作しても大丈夫?
A. システムパーティション(/)やマウント中のパーティションは、ライブシステム上では拡張できない場合があります。可能であればライブUSB(Ubuntuのインストールメディアなど)から起動し、操作を行うのが安全です。
クラウドやVPSの多くはマウント中でもオンラインで拡張できますが、エラーが出る場合は一時的にアンマウントや再起動が必要なこともあります。
Q5. swap領域がパーティション拡張の妨げになっています。どうすればいい?
A. swapがUbuntuパーティションの隣にある場合、swap領域を一時的に無効化(swapoff)し、削除してから操作を進めます。拡張後に必要であればswapを再作成し、/etc/fstabを修正してください。
Q6. 仮想環境でディスク容量を増やしたのに、OS上で反映されません。なぜ?
A. 仮想環境では、ハイパーバイザー(VMware、VirtualBoxなど)でディスクを拡張した後、OSから新しい容量を認識させる必要があります。echo 1 > /sys/class/block/sdX/device/rescan や、再起動、または partprobe コマンドで再スキャンしてください。
Q7. GPTとMBRの違いは?どちらを選べばいい?
A. GPTは2TB以上の大容量ディスクや多数のパーティションに対応した新しい方式で、現在はほとんどの環境でGPTが推奨されます。MBRは古いシステムとの互換性が必要な場合のみ選択しましょう。
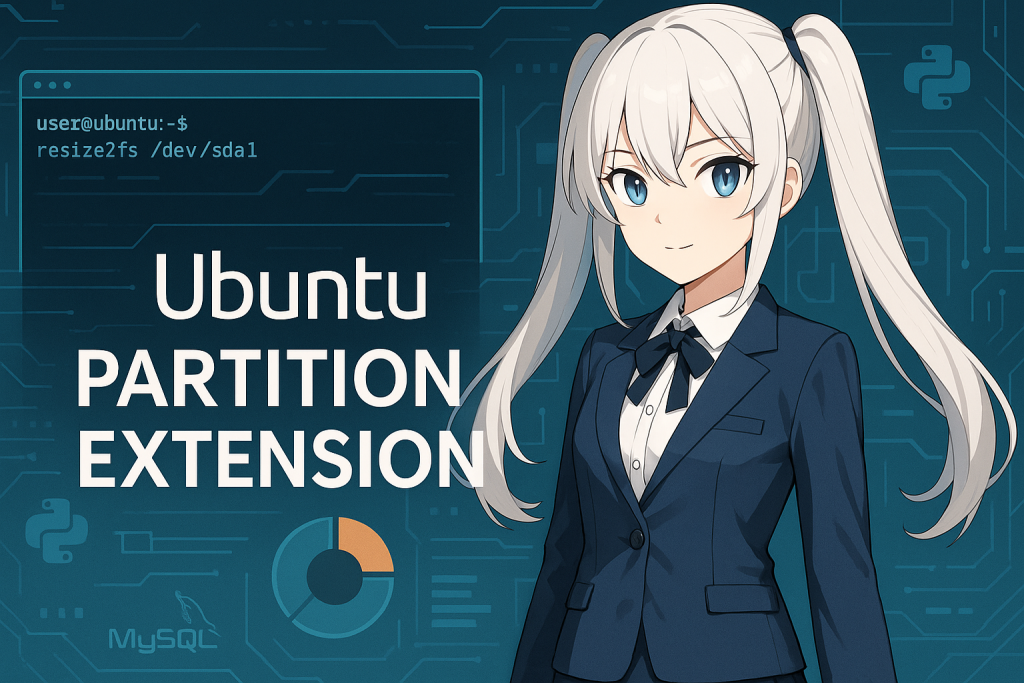
4.2 代表的なエラーと対処例
- “no free space available”
→ 隣接する未割り当て領域が必要。位置を調整して再実行。 - “device is busy”や“resource busy”
→ パーティションがマウント中、もしくは利用中。アンマウントやライブUSBで作業してください。 - “The partition is currently in use”
→ 対象のパーティションが使用中。対象サービスやOS自体を一時停止・再起動し、再度実行。 - “resize2fs: Bad magic number in super-block”
→ パーティションの種類とコマンドの組み合わせが正しいか再確認。xfsファイルシステムではxfs_growfsを使う必要があります。
このようなトラブルや疑問も、事前に知っておくことで冷静に対処できるようになります。必要に応じて本記事の手順を見直したり、公式ドキュメントや信頼できるサイトも活用しましょう。
5. 実行後の確認・まとめ
パーティション拡張の作業が完了したら、最後に必ず拡張結果の確認を行いましょう。操作ミスやトラブルによる不具合がないかチェックすることで、大切なデータやシステムの安定性を守ることができます。
5.1 拡張結果の確認方法
(1) ディスクの容量確認df -hコマンドを使うと、現在マウントされている各パーティションの使用量と空き容量を一覧表示できます。拡張したパーティションの容量が正しく増えているか確認しましょう。
df -h特に、「/」や「/home」など、拡張したい領域が期待通り増えているかを見てください。
(2) パーティション構成の確認lsblkコマンドは、接続されているストレージデバイスやパーティション構成をツリー表示します。パーティションサイズやレイアウトが正しく反映されているか確認できます。
lsblk(3) partedによる詳細確認sudo parted /dev/sda print freeなどで、パーティションテーブルや未割り当て領域も含めたディスクの状態を詳細に確認できます。
(4) LVMの場合の追加チェック
LVMを利用している場合は、sudo lvsやsudo vgsコマンドでボリュームグループや論理ボリュームのサイズも確認しておきましょう。
5.2 作業後の注意点
- バックアップデータの管理
パーティション拡張が問題なく完了し、データやシステムの動作に異常がなければ、一時的に取得したバックアップデータは整理・削除しても構いません。ただし、不安が残る場合は一定期間バックアップを保管しましょう。 - ファイルシステムの検査
万が一のトラブルや不具合に備えて、fsckコマンドなどでファイルシステムチェックを行うこともおすすめです。
sudo fsck /dev/sda1(※マウント解除してから実行してください)
- 再起動の有無
基本的に、拡張後は再起動不要ですが、仮想環境や一部の物理マシンではOSの再起動を行うことで、新しいディスクサイズが完全に認識される場合もあります。
5.3 まとめ
Ubuntuでのパーティション拡張は、事前の準備と正しい手順さえ押さえておけば、意外とスムーズに進めることができます。万が一のトラブルにも対応できるよう、作業前のバックアップや確認手順をしっかり踏んで、安心してディスク容量を増やしましょう。
パーティションやストレージの管理は、システム運用や日常利用の中でもとても大切な作業です。本記事の内容が、みなさんの環境で役立つことを願っています。